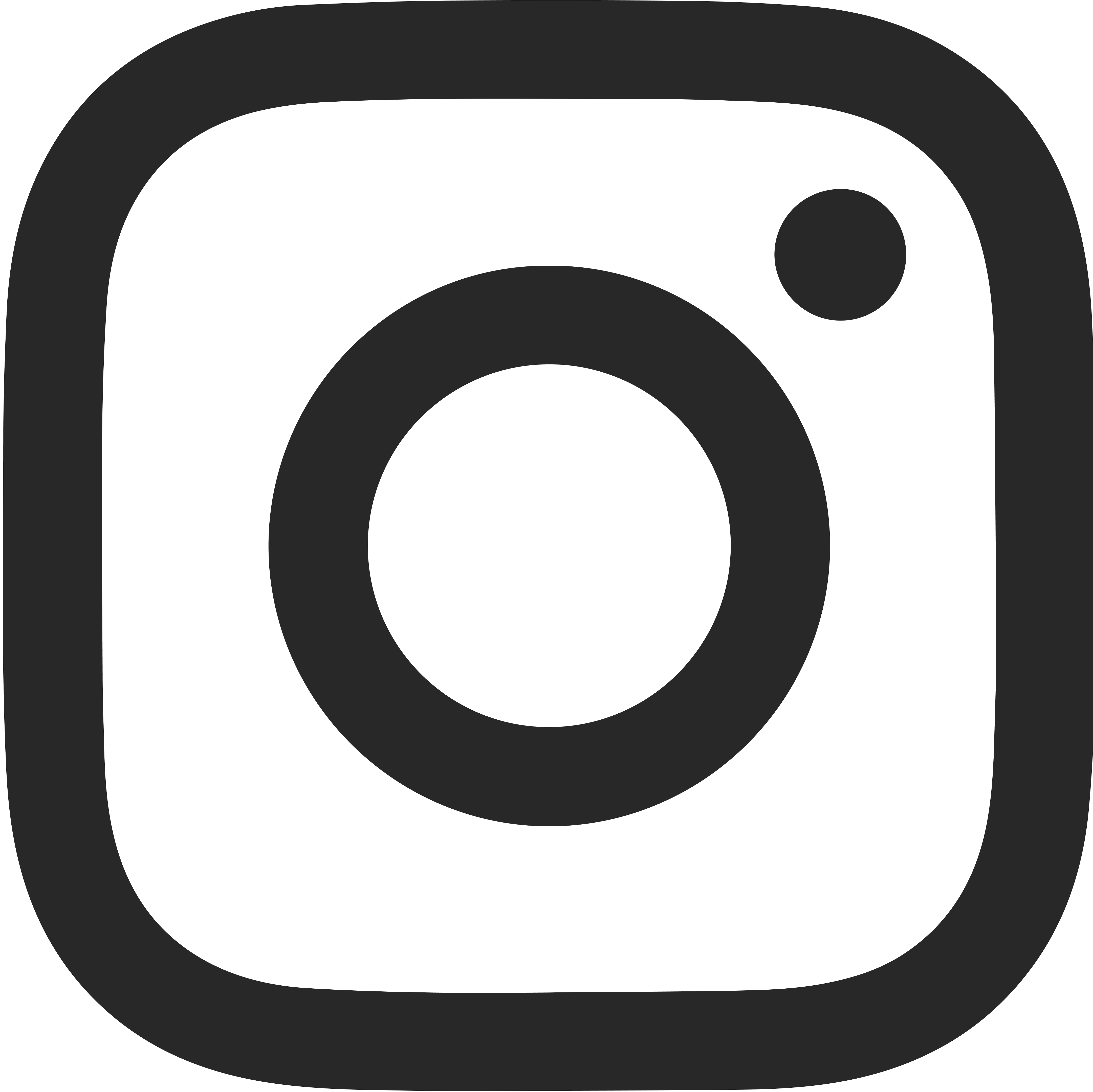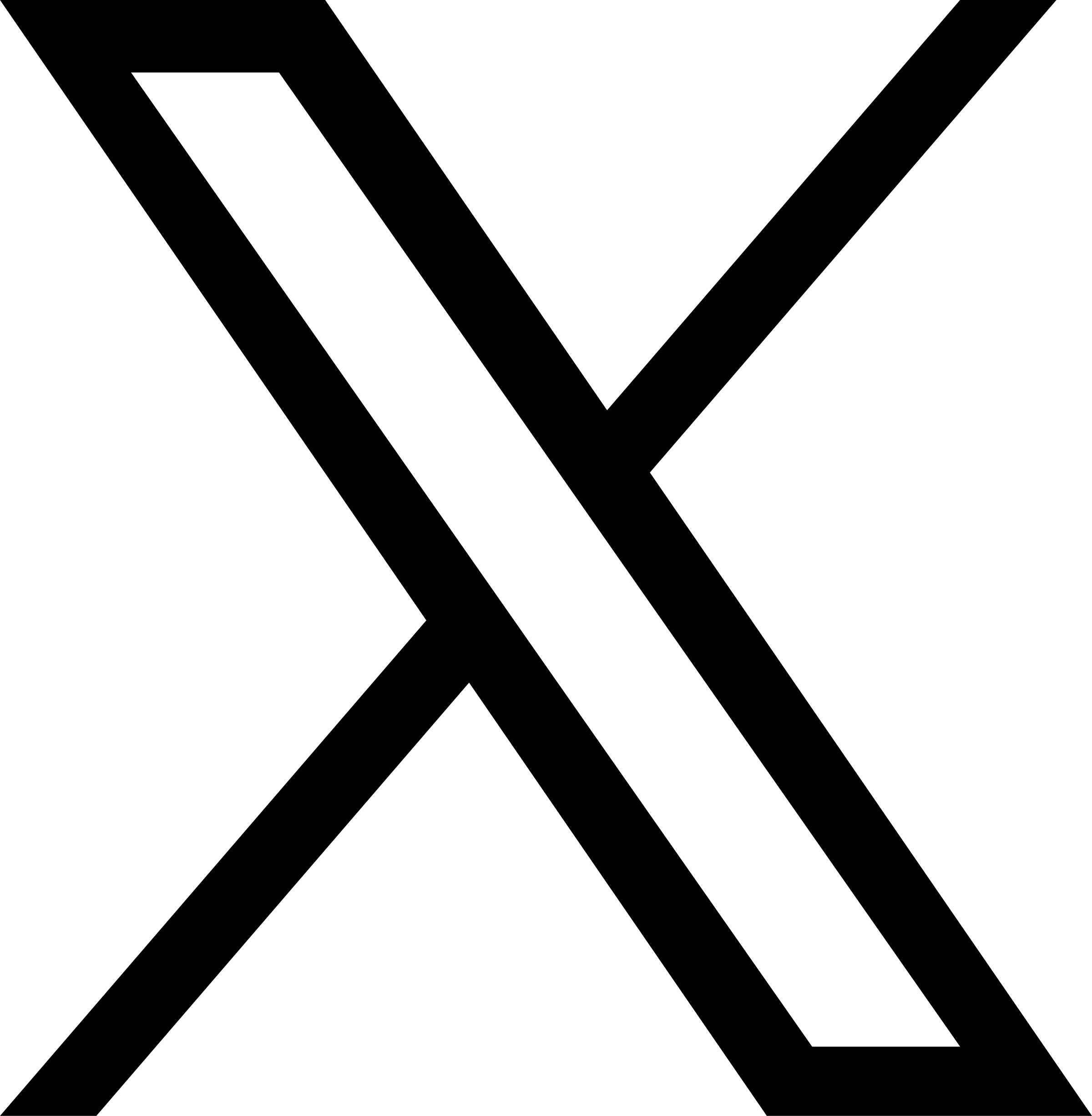日本海、太平洋、むつ湾と、3つの海に面する青森県。そのほぼ中央に位置するむつ湾は、東に下北半島、西に津軽半島、中央に八甲田山系の自然豊かな環境があり、山々から流れる川からはミネラルたっぷりの水が注ぎ込まれる。この恵まれた環境の中で育まれ、青森県の水産業の基幹となっているのがホタテ養殖だ。
そんなむつ湾で養殖から水揚げ・加工まで一貫して行っている「株式会社山神(やまじん)」は、「ホタテ観を変えてゆけ」というキャッチコピーを掲げ、ホタテの可能性に挑戦し続けているという。
今回、新たに開発した商品が常温保存できる「うまみたっぷりほたて」だ。商品にかける想いを聞きに、青森市を訪ねた。
ホタテの旨みを最大限に引き出すためのこだわり

漁師の先代が1993年に創業した「株式会社山神」は、むつ湾に面する青森市油川地区に2つの加工工場を構え、「ホタテ本来のおいしさを知るからこそ、加工の過程で妥協はしない」という想いで水揚げから加工まで一貫した生産を行っている。
栄養豊富なむつ湾の海水で1枚1枚手間ひまかけて育てるホタテは、肉厚な貝柱で、とろけるような甘さとぷりぷりとした食感が特長だ。
山神では、さらにホタテが持つ旨みを引き出すためのこだわりがあるという。
「まずは旬、そして鮮度、滅菌海水、衛生面、最後に人の手です」と語るのは、専務取締役本部長の穐元美幸さん。
「ホタテは真水に触れると白くなり、旨みとなるエキスが出てしまうんです。でも、海水であれば、浸透圧で旨みが逃げません。そこで、弊社の製造工程ではすべて、すぐそばのむつ湾から汲み上げた海水を滅菌処理して使用しています。ウロと呼ばれる黒い部分を一粒一粒手で取って、サイズ選別も手作業です。ホタテはとても繊細で、その日の気温や湿気によって質感が変わってしまうんです。だから、ホタテに触れる力加減を調節できるのは、人の手だけなんですよ」
山神では、社屋のすぐそばにある漁協組合から水揚げされたばかりのホタテを入荷し、抜群の鮮度のまま海水で旨みを閉じ込め、手間ひまかけて加工している。このこだわりが、山神の大きな強みとなっているのだ。
むつ湾で育つホタテを世界へ

山神では業務用の冷凍貝柱とベビーボイルホタテをメインに生産を行ってきたが、2010年東北新幹線新青森駅の開通を機に、お土産となる個人に向けた商品の展開をスタートし、いち早くECサイトでの販売も開始した。
「業務用の商品だけでは、ホタテの品質の良さや自社製品のこだわりがなかなか伝わらないと感じていたんです。商品にもっと付加価値をつけたいと思い、冷凍食品のホタテフライや、ホタテ飯の素、ホタテオイル漬けの瓶詰めなど、ホタテのおいしさをダイレクトに感じていただける商品を作り始めました。最近では、ホタテの貝殻を再利用して化粧品や洗剤などの開発にも取り組み、新たな分野にも踏み込んでいます」と穐元さん。

ホタテをよく食べる東南アジア圏はもちろん、アメリカ、これまで業界が足を踏み入れてこなかったEU圏にもいち早く目をつけ、展開を仕掛けているという。青森ほたての美味しさを世界に届けようと、フランス語で書かれたほたてのレシピ集まで準備しているのだ。
無駄なく、安定してホタテを供給するために
「ホタテを使ったモノづくり」を掲げて邁進していた山神だが、2023年、むつ湾に異変が起こった。記録的な猛暑にともなうむつ湾の水温上昇によって、ホタテの稚貝が大量へい死する事態が起こったのだ。

「実は、2012年にも大量へい死がありました。そのときから、気候変動によって今後むつ湾の海に異変が起こるかもしれない、ホタテが獲れない未来はきっと来ると思っていたんです。だからこそ、当時から自分たちがやれることに取り組んできました。
今回の大量へい死をきっかけに、これまで以上に資源ロスの抑制や安定して商品を届けるための研究を進めています。その一環として、安定的な原料の供給を目指して、超低温フリーザ―を導入し、ホタテ本来の旨みを保ちながら、解凍後に旨みを逃がさず、長い賞味期限を実現できるレトルト商品の開発に取り組みました」。
自然環境の変化は、避けては通れない。環境の変化に対応して、どう資源を次の世代へつなげていくか。自分たちの商売はもちろん、青森県の基幹産業として多くの人の生活を支えるホタテの養殖業を守るため、新たな商品作りが始まった。
文・鈴木麻理奈 写真・世永智希 (5枚目 山神提供)