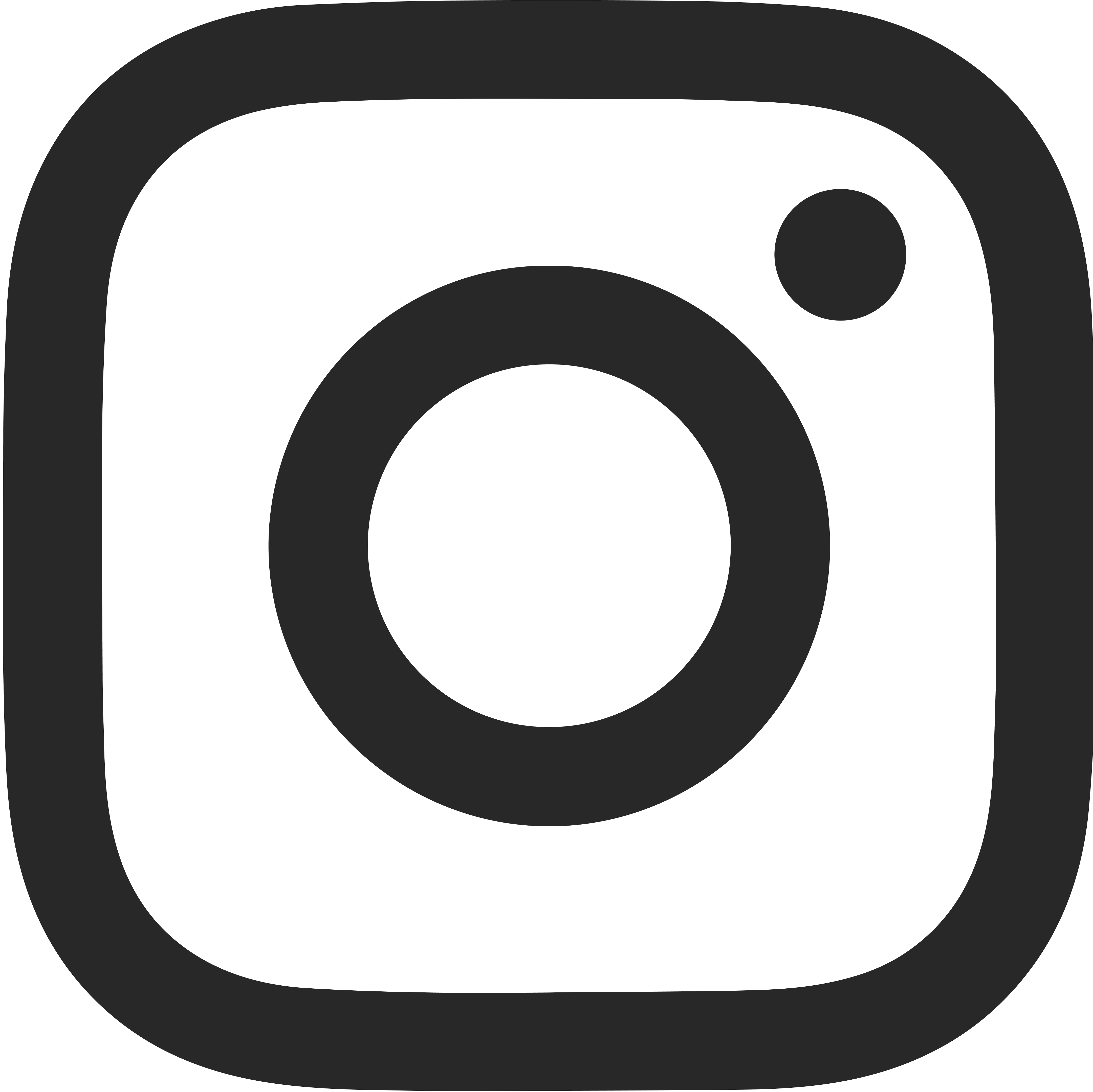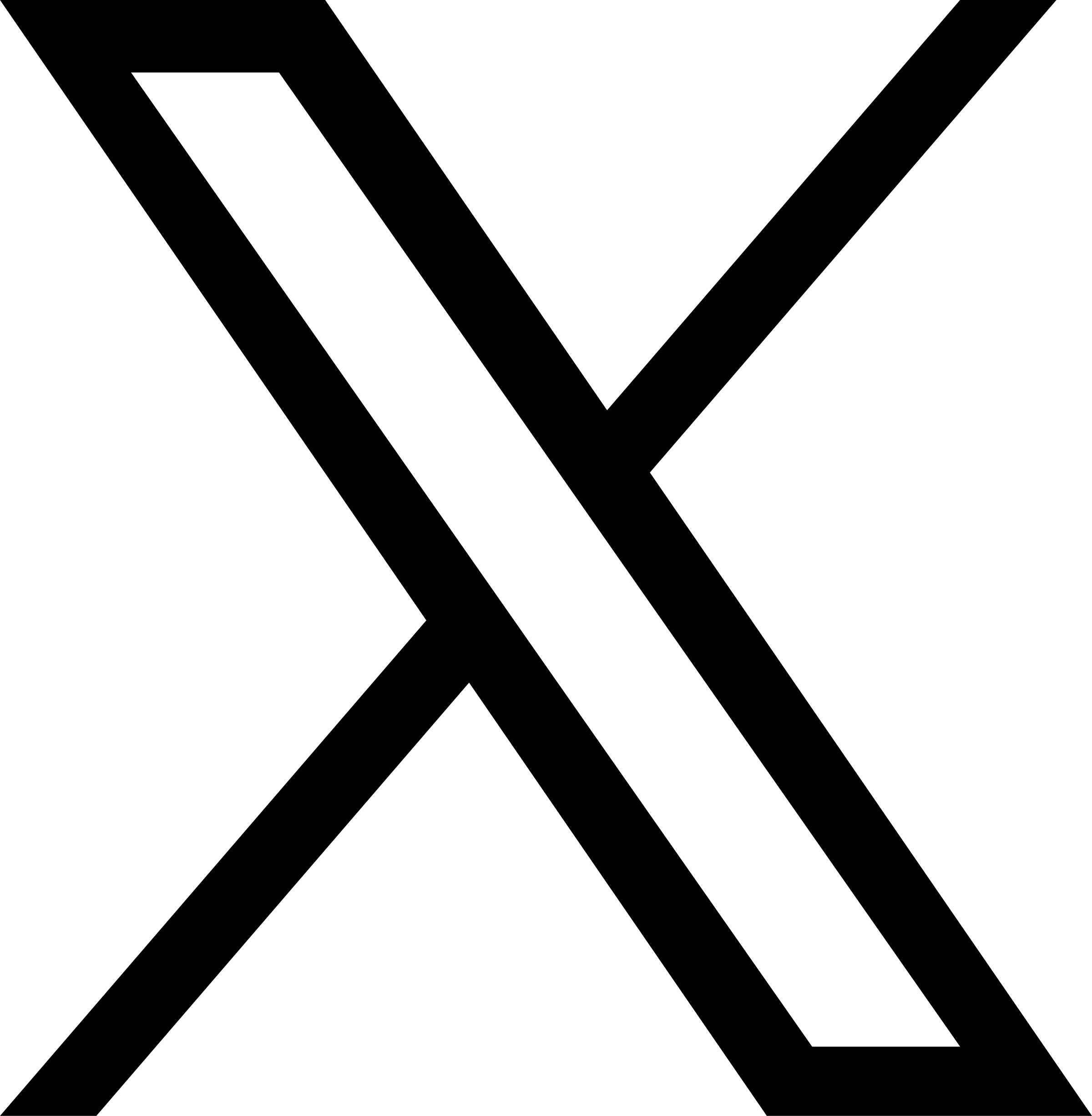岩手県沿岸中央部の三陸地方に位置する山田町。面積の大半を森林が占め、その養分が3本の川を通じて山田湾にたっぷりと流れ込むため、昔からカキやホタテの養殖が盛んな町だ。
2006年に水産加工会社として創業した「株式会社川石水産」は、町内産を含む三陸産のホタテを使った「ほたてグラタン」が看板商品となっている。ホタテの殻を「器」にし、貝柱入りの自家製グラタンソースを盛り付けて冷凍したものだ。
ところが、ここ数年その「器」用の殻を確保するのが難しくなってきているという。また、殻を使うことによる資材のロスやリサイクル処分の負担といった問題も発生している。
そこで、ホタテの殻の代わりにパンを使って丸ごと食べられる新商品を開発し、殻不足や環境負荷などの社会問題の解決を目指しているという。開発に携わった取締役工場長の平賀雅崇さんに詳しい話をうかがった。
入手困難な殻に代わる「器」を!

川石水産では、殻付きのホタテを仕入れ、殻を器に中身の貝柱をグラタンに利用して「ほたてグラタン」を製造してきた。
ところがホタテの殻は、仕入れたすべてが器として利用できるわけではなく、ある程度の大きさと深さが必要なため、商品となるのは仕入れた分のわずか2割程度。さらに近年はホタテの水揚げ量が減少し、サイズが小さくなっていることから、近い将来入手困難になることが予想されるという。
「しかも、殻はそのまま使えるわけではありません。殺菌をしたら、ブラシでこすったりたたいたりして付着物を落とし、端を切って形を整えます。これらの作業は機械では不可能で、すべて手作業なのでコストもかかるんです。また、お歳暮の時期などにほかの作業が重なると殻の加工ができなくなり、グラタンが欠品してしまうという事態になることもありました」と平賀さん。

ホタテの殻を使う際の問題は、ほかにもある。冷凍状態の商品は真空包装し、衝撃から守るため発泡スチロールの箱に入れて発送するのだが、真空袋に殻の角が当たり、袋が破れてロスが出るのだ。
また、発泡スチロールは体積が大きいので輸送・収集コストがかかるうえ、納品先からも「リサイクル処分が面倒なので、別の資材を使ってほしい」という声があがっていたという。
1石3鳥4鳥の「パンの器」
ホタテの殻に代わる「器」が必要だ。そこで平賀さんが思いついたのが「パン」だった。
以前、「ほたてグラタン」がテレビの全国放送に取り上げられた際、試食したアナウンサーが「パンと一緒に食べたらさらにおいしいですよね!」とコメントしたことがあった。それを聞いた平賀さんは、後日フランスパンに合わせて食べてみた。すると、アナウンサーのコメントどおり、よりおいしく味わうことができたという。「その時の体験を思い出し、社長に提案してみたんです」と当時を振り返る。

殻をパンに代えれば、殻をこすったり切ったりする工程や人件費を削減できる。また、真空袋が破れるリスクが少ないので、袋のロスや発泡スチロールの使用を減らすことができ、環境負荷の軽減にもつながる。さらに消費者にとっても、丸ごと食べられるという手軽さと、殻の破棄が不要という点は魅力だ。1石2鳥どころか3鳥、4鳥にもなる平賀さんのアイデアに、川石睦社長も賛同し、すぐに開発がはじまった。
「パンの形が崩れる」という問題が
パンの製造は、同社の販売部門・川石商店が立地する奥州市水沢のパン店に委託した。川石社長はふだんから、地元企業や取引企業とのつながりを大切にしており、このパン店もその1軒だった。パンの種類や形などは、パン店と川石社長、川石商店の惣菜開発担当者との間で話し合い、さまざまな種類を試した結果、長さ約19㎝、厚さ1~2㎝の細長いボート型のフランスパンに決定したという。

平賀さん曰く「このパンに決定するまでかなり時間がかかった」そうだが、もっとも苦労したのは、実はそのあとだった。
殻を使った「ほたてグラタン」を製造する時は、殻にグラタンソースを盛り付けてオーブンで加熱調理し、冷まして冷凍する。そこでパンでも同様の工程で進めてみたのだが、グラタンソースを盛って加熱調理すると、パンがソースの水分を吸ってベチャベチャの状態になってしまうのだ。
試作後から平賀さんは数週間かけて試行錯誤を繰り返したという。そして、最終的にたどり着いたのが、従来とは異なる調理工程だった。
文:赤坂環 写真:川代大輔