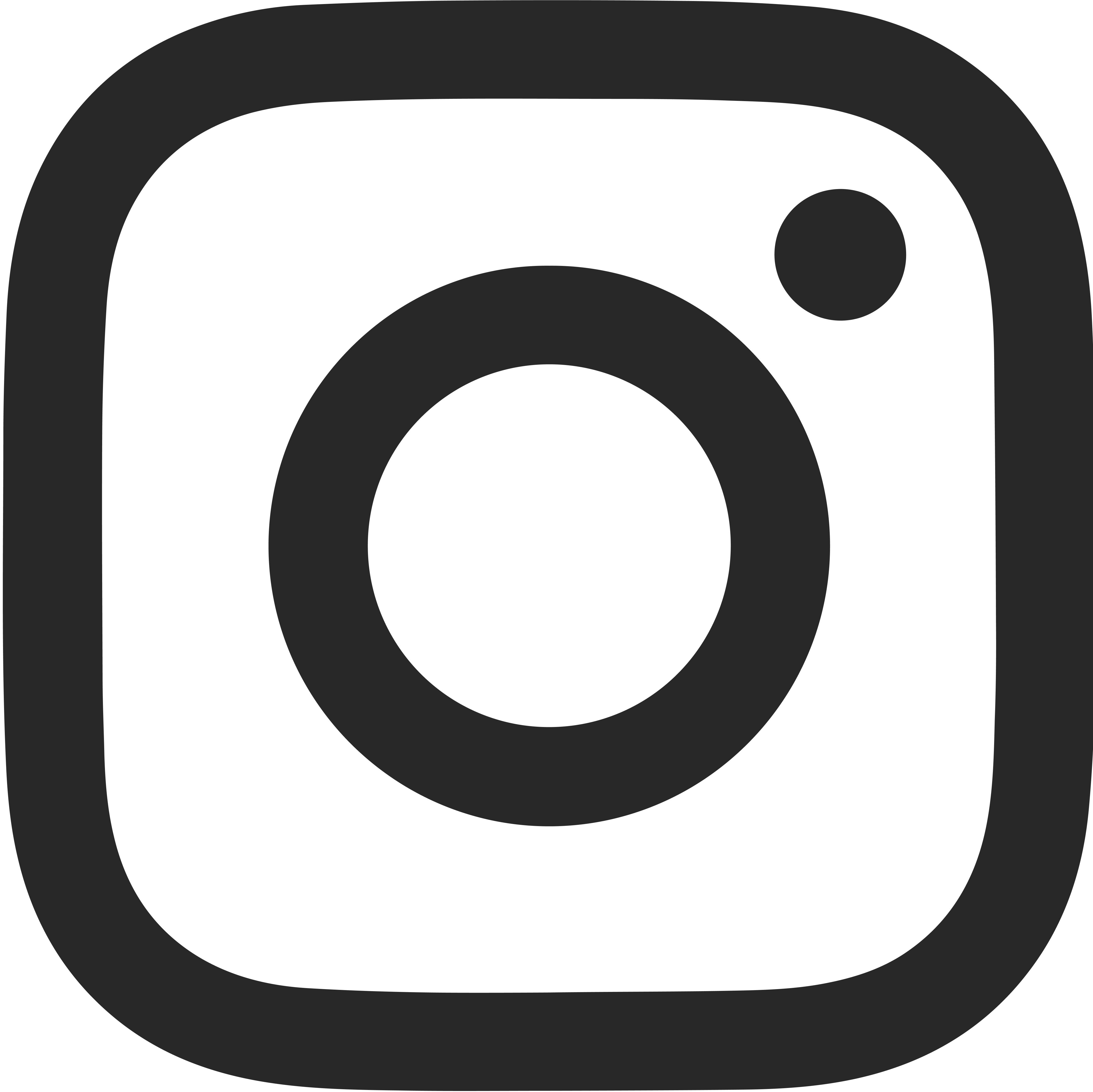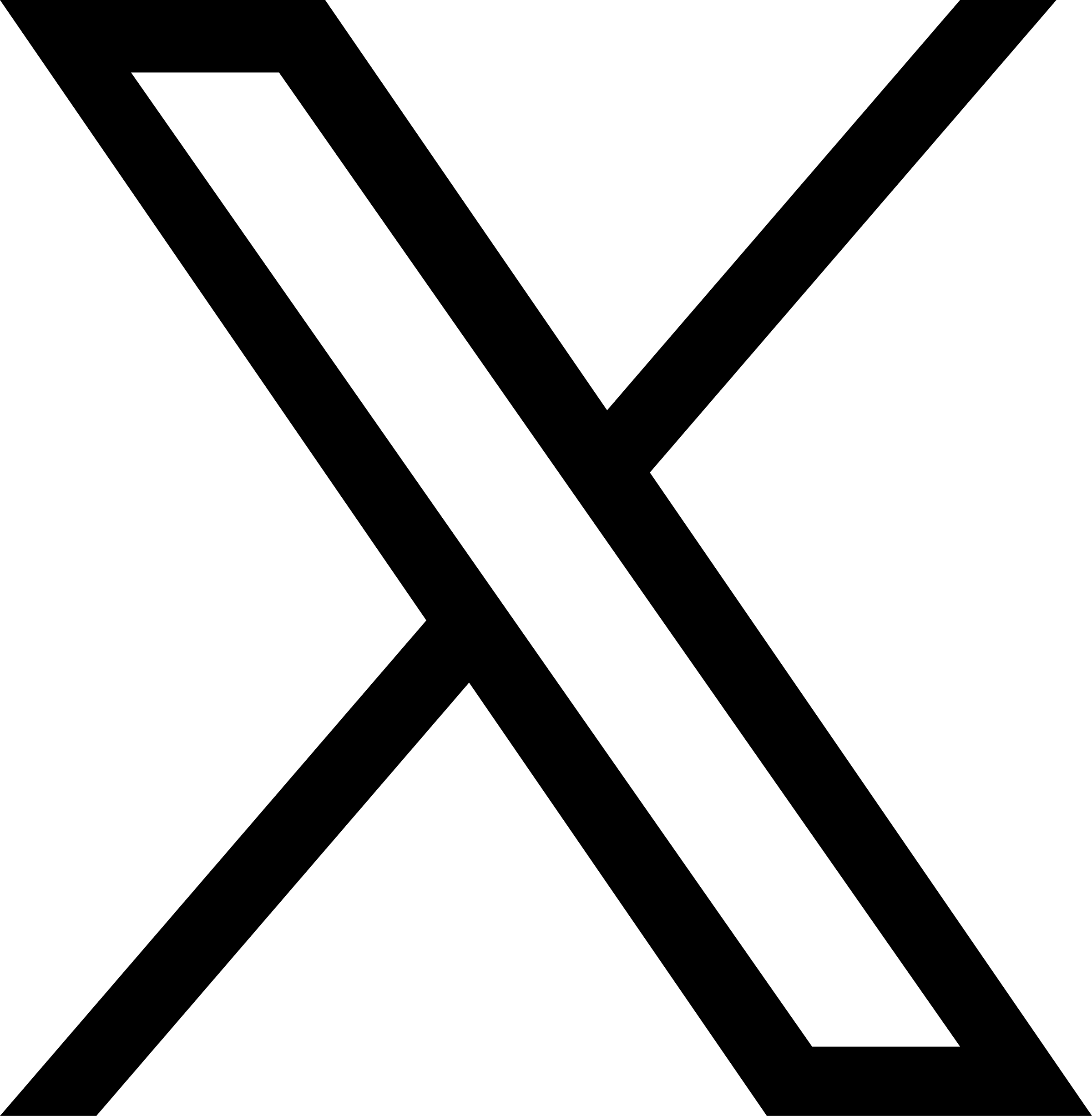冬のはじまりの福島県相馬市・松川浦。日本百景のひとつにも選ばれている県内唯一の潟湖は鏡面のように輝いていた。12月からはじまる収穫最盛期を前に、ひすい色のアオサの養殖棚が広がっている。
「アオサの収穫がはじまると、浜で天日干しする様子が見られます。とても良い香りがするんですよ」
そう話すのは、松川浦のほとりにある中澤水産有限会社の営業担当・中澤久仁彦さんだ。東京の大手住宅設備メーカーに勤務する会社員だったが、父のあとを継ぐために退職し、2022年4月、ふるさとに戻って来た。
そして、一足早く帰郷していた弟・由樹さんとともに兄弟ふたりで生み出したのが、「常磐もの」ブランドの「ヒラメ」と目の前の浜で採れる「アオサ」を使った「平目と生海苔の海鮮ぶっかけ丼」だ。
「商品のかなめは仲買人の父が目利きする魚の仕入れです。市場の競りの様子は見ごたえがありますよ」という久仁彦さんに誘われて、早朝の魚市場に向かった。
目利き一筋40年の父がいる市場の風景

11月上旬の相馬原釜魚市場。この日は早朝から刺網、釣り、沖合底引き網と立て続けに水揚げがあり、それぞれ競りが行われていた。競り会場には、6キロ超の大きなヒラメやタイ、カナガシラといった高級魚や季節の魚がずらり。海水温の変化で近年出はじめた天然のトラフグやワタリガニも常連になっており、場内は水揚げされたばかりの魚でいっぱいだ。

鐘の音とともに競りがはじまると、仲買人たちがひしめき合いながら場内を移動し、魚を見定めていく。その中心にいたのが久仁彦さんの父で社長の正英さんだ。冗談を言って周囲を和ませつつも、魚を見る眼差しは真剣そのもの。そして何より、瞬間の駆け引きを楽しんでいるのが分かる。

「父は大学を出てすぐに仲買人になり40年間、目利き一筋です。震災で市場が閉鎖されていた時も千葉の関連会社で働いており、寝ても覚めても魚。魚を見てないときがないぐらいです」と久仁彦さん。“目利き”の正英さんが競り落としたヒラメは、肉厚で身が締まっているうえ、脂がのっていておいしいと評判が高い。
「常磐もの」ブランドの活魚を全国へ

魚市場からほど近い、松川浦の目の前に会社を構える中澤水産は創業1975年(昭和50年)。久仁彦さんの曽祖父がふるさと相馬原釜港で仲買人の仕事をはじめ、父正英さんが3代目という。
東京の旧築地市場をはじめ、全国の市場を中心に販路を拡大し、鮮魚・加工品と幅広い商品をそろえるが、1番のウリは何といっても活魚(かつぎょ)だ。会社の一角にある巨大な活魚水槽は相馬市唯一の規模を誇る。ここに松川浦から引き込む海水で商品を保管し、専用トラックにいけすのまま荷積みするため、鮮度を落とさずに商品を運搬できる。


相馬沖は、黒潮と親潮がぶつかり合う潮目の海で、プランクトンが育つ天然の漁場が広がっている。震災前の海面漁業生産統計調査によれば、相馬原窯産のヒラメ・カレイ類の漁獲量は全国1位(平成21年度)。かつては多くの魚種が上位に入っていた。これらの商品を中澤さんら歴代の仲買人たちが首都圏の市場に積極的に売り込むことで、福島県の「常磐もの」ブランドを築き上げてきたのだ。

中でも「常磐もの」を代表する魚が「ヒラメ」だ。刺身やカルパッチョなど和洋さまざまな食べ方があり、脂がのりつつ、身が引き締まっておいしい旬の冬は特に高値で取り引きされる定番商品のひとつだった。
それが一変したのが、2011年の東日本大震災だ。
文・写真 荒川涼子