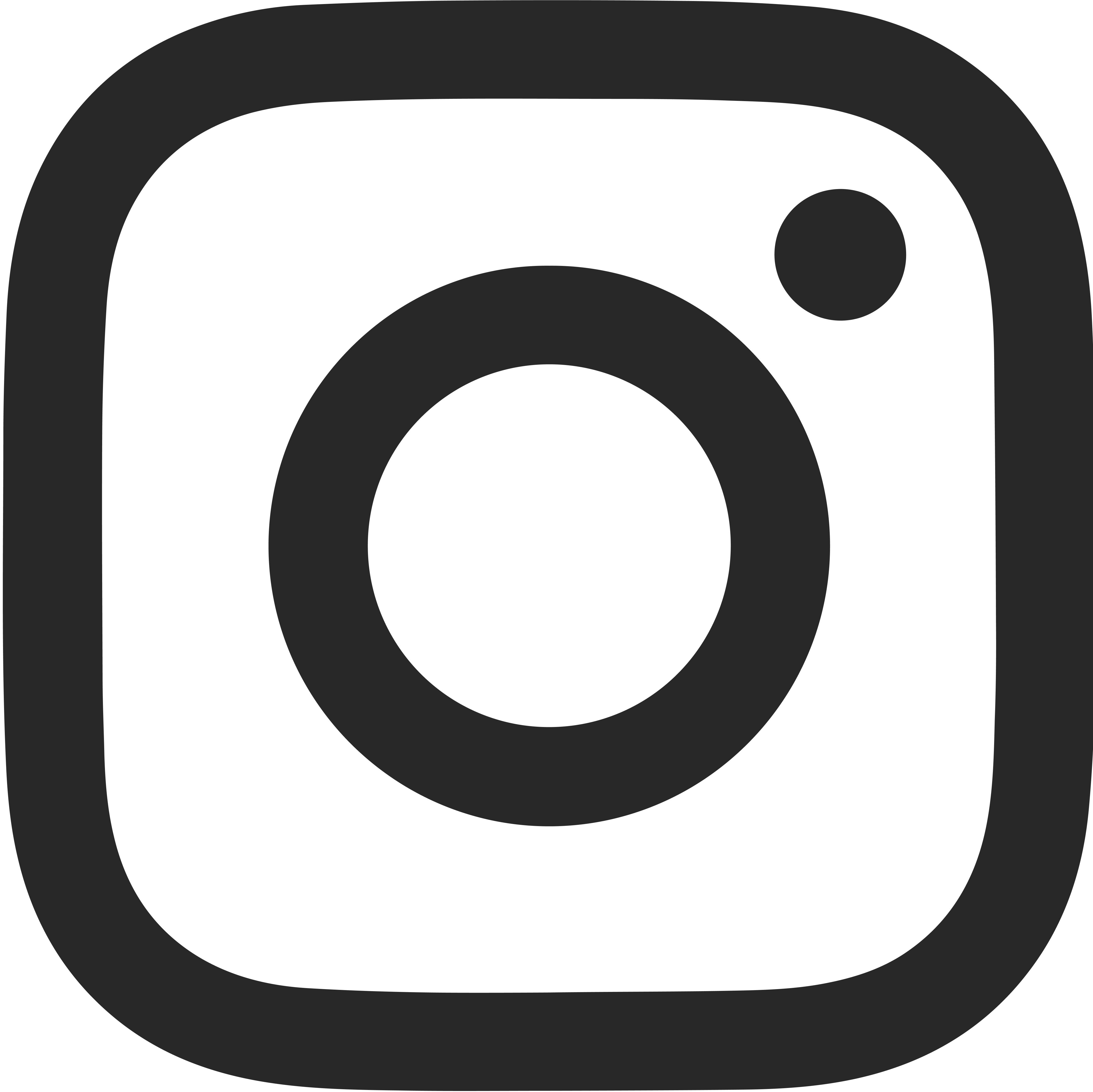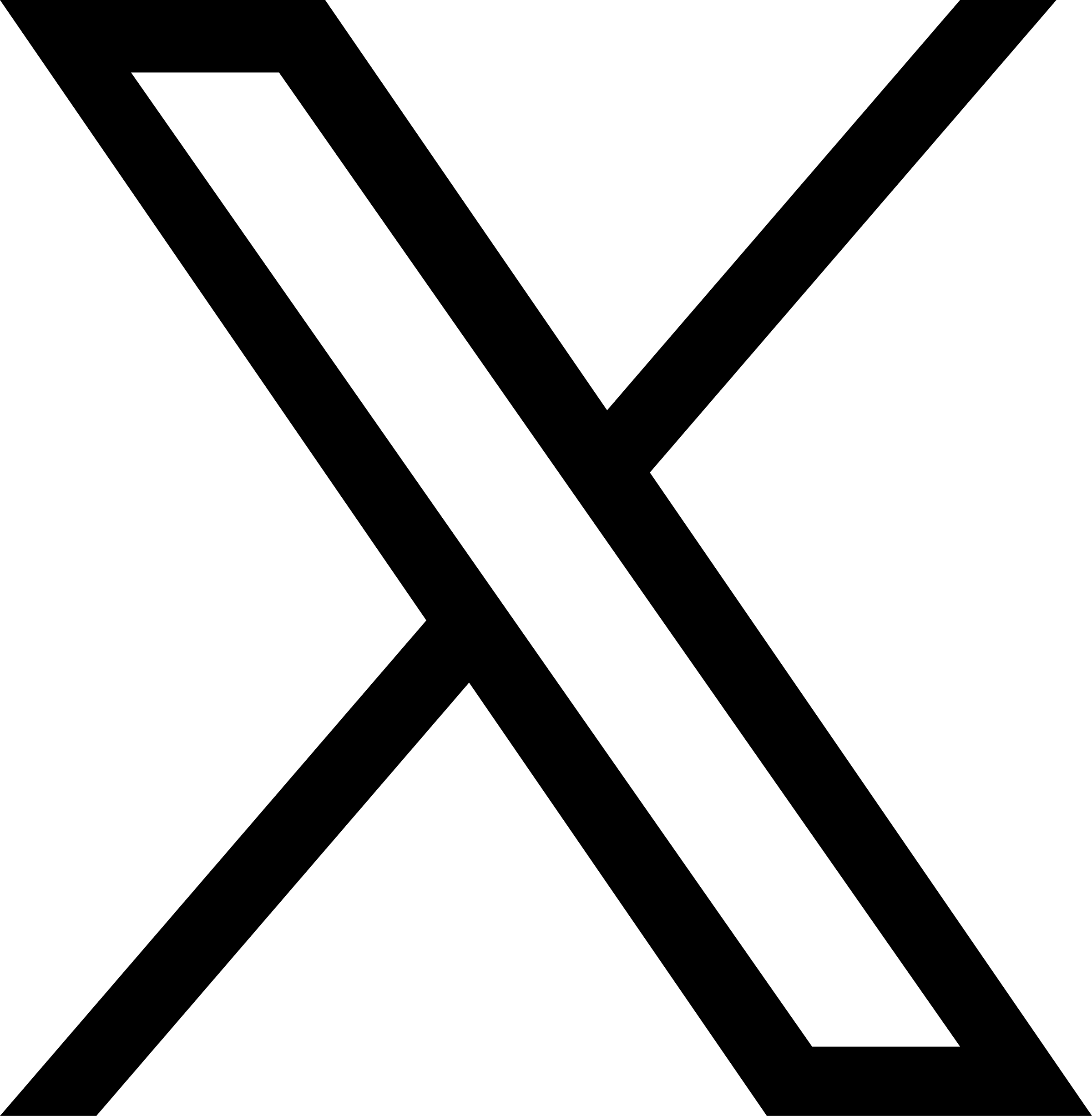「お茶漬けとしての完成度」を高めたい

ギフトセットとして売り出す予定のお茶漬けは、年末のお歳暮商戦に向けて日々試作を繰り返している。商品開発に深く関わっている遠藤さんによると、「味のバランス調整」についてはとくに苦労しているそうだ。

干物は非常にデリケートな食品だ。塩水の漬け込み時間や乾燥の具合が少し違うだけで魚の水分量が変化し、最終的な仕上がりに影響する。
自慢の魚を多くの人に味わってほしいと思う一方、品質には妥協をしない。魚をほぐして食べた時に口の中で一体感が得られるよう、干物とご飯、かやく、だし汁のちょうどいいバランスを探っている。
「干物そのものではなく、あくまで干物のお茶漬けを食べていただくことが目的です。しかし、私の魚へのこだわりが強すぎるあまり、今はまだ魚そのものの存在感が強くて(笑)。今後はもっと全体的に調和させていき、お茶漬けとしての完成度を高めていきたいです」と間宮さんは話し、さらなる品質向上への意欲を見せた。

現在開発中の3種類が軌道に乗ったら、より種類を増やして展開する予定だ。
その構想のなかには、「未利用魚」を使ったお茶漬けの開発も含まれる。未利用魚とは、漁獲量が少ないなどの理由から水揚げされても活用されない魚のこと。昨今、温暖化の影響からこれまで地元では見かけなかった魚が水揚げされる機会がふえているのだそう。同社ではその活用方法の一つとして、お茶漬けへの加工を検討している。
「魚を扱う企業として、さまざまな方法で魚のおいしさを伝えたい。魚をこれからもお客さまに届けたい」と、終始熱い想いを語る間宮さん。魚への愛情、こだわりの深さから地元では、間宮商店ならぬ「マニア商店」と呼ばれることもあるほどだという。
目利きを生かし、干物の卸売から始まった歩み

間宮商店は1966年創業。間宮さんの父であり初代社長の明夫さんが、干物店を開いたことからその歴史が始まった。1979年には法人化し、順調に事業を拡大。間宮さんも幼少期から漁港へ連れて行かれ、せりの様子を間近で見ていたという。その後は、築地魚市場で鮮魚のせり人として3年間ほど修行。学んだ魚の知識や目利きを生かし、2015年からは二代目として手腕を振るっている。
もともと卸売を専門としていたが、2005年にオンラインショップ「さんりく干物や間宮塩蔵」を開設してからは客層が広がり、一般客が商品を購入する機会が増えた。この頃から徐々に一般客向けの事業展開も進め、「お客さまに笑顔になっていただき、びっくりしてもらえるような取り組みを大事にしたい」という考えが強まった。
東日本大震災では、機械が倒れて故障したり、敷地内の地面が割れたりなどの被害を受けた。被災をきっかけに社屋と工場の移転を決め、2014年7月、工場併設の直営店オープンとともに新社屋にて新たなスタートを切った。
「うみおむすび」で客層が広がる

直営店内では主に冷凍の干物を販売していたが、「もっと干物や魚を身近に感じてもらいたい」という想いから、2016年に直売所限定で「うみおむすび」の販売を開始。三陸産の金華サバやイワシ、塩釜の藻塩を使ったたらこなど、海のまち・塩釜ならではの魅力をぎゅっと詰め込んだ。
レギュラーメニュー10種類に加え、時期による限定メニューもある。それらが毎日店頭に並ぶ。価格帯は1個あたり150円から300円と、コンビニエンスストアで販売されるおにぎりよりは高めだが、12時前にはほぼ売り切れるほどの人気ぶりだ。
来店する客層にも変化があった。それまでは購買層のほとんどが40代以上だったが、うみおむすびを求めて子どもから高齢者まで幅広い年代が足を運ぶようになったという。
筆者は、一番人気の「金華さば(甘粕)」を食べてみた。真っ先に驚くのは、その具の大きさだ。なにせ、食べる前から具がのぞいている。ひと口、ふた口と食べ進めても満足感は一向に目減りしない。おむすびの中いっぱいに具が詰まっていて、どこを食べてもおいしいのだ。しかも口の中に入れると身がほろほろと解け、食べやすい。当然、味は言わずもがな。甘粕の自然な甘みと、サバ本来の味わいがちょうどよくマッチしてとにかくご飯と合う。余計な味つけをしていないから素材の味が際立ち、だからこそおいしい。

「魚屋が作るおむすびだから、中途半端にはしたくない」という間宮さんの言葉がすとんと腑に落ちた。連日売り切れでも納得、むしろ全種類食べ尽くしたいと思わせてくれる逸品で、お茶漬けの完成も俄然楽しみになった。
温暖化などの影響から漁獲量が減少し、それに伴い魚の価格が上がっている。間宮さんは「お客さまに適正な価格だと感じてもらえるよう、作り手側も努力していかなければ。毎日でも食べたいと思ってもらえる商品を作り、お客さまに笑顔と驚きを届けていきたいです」と力強く展望を語ってくれた。
文・岩﨑尚美 写真・株式会社ル・プロジェ