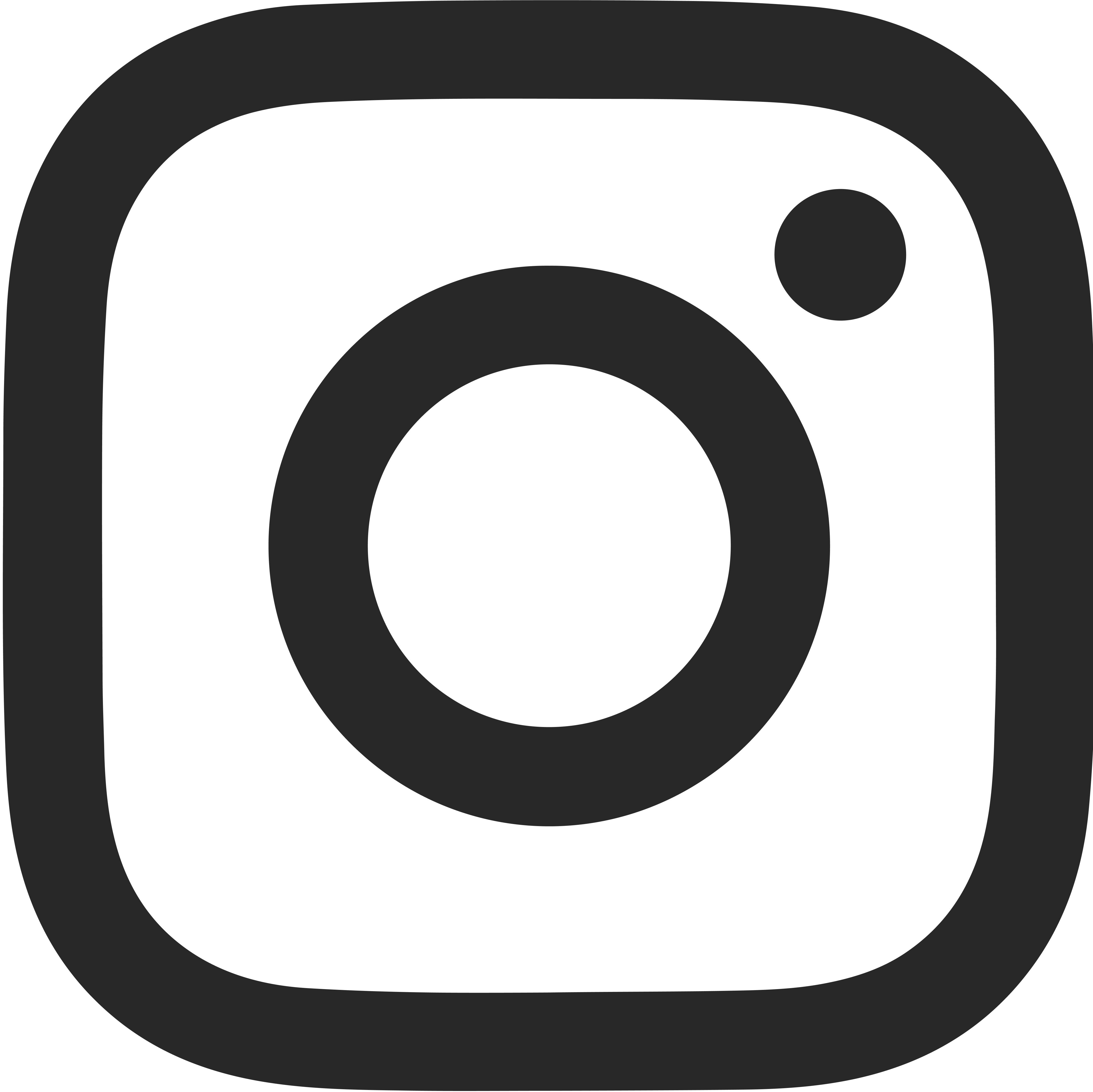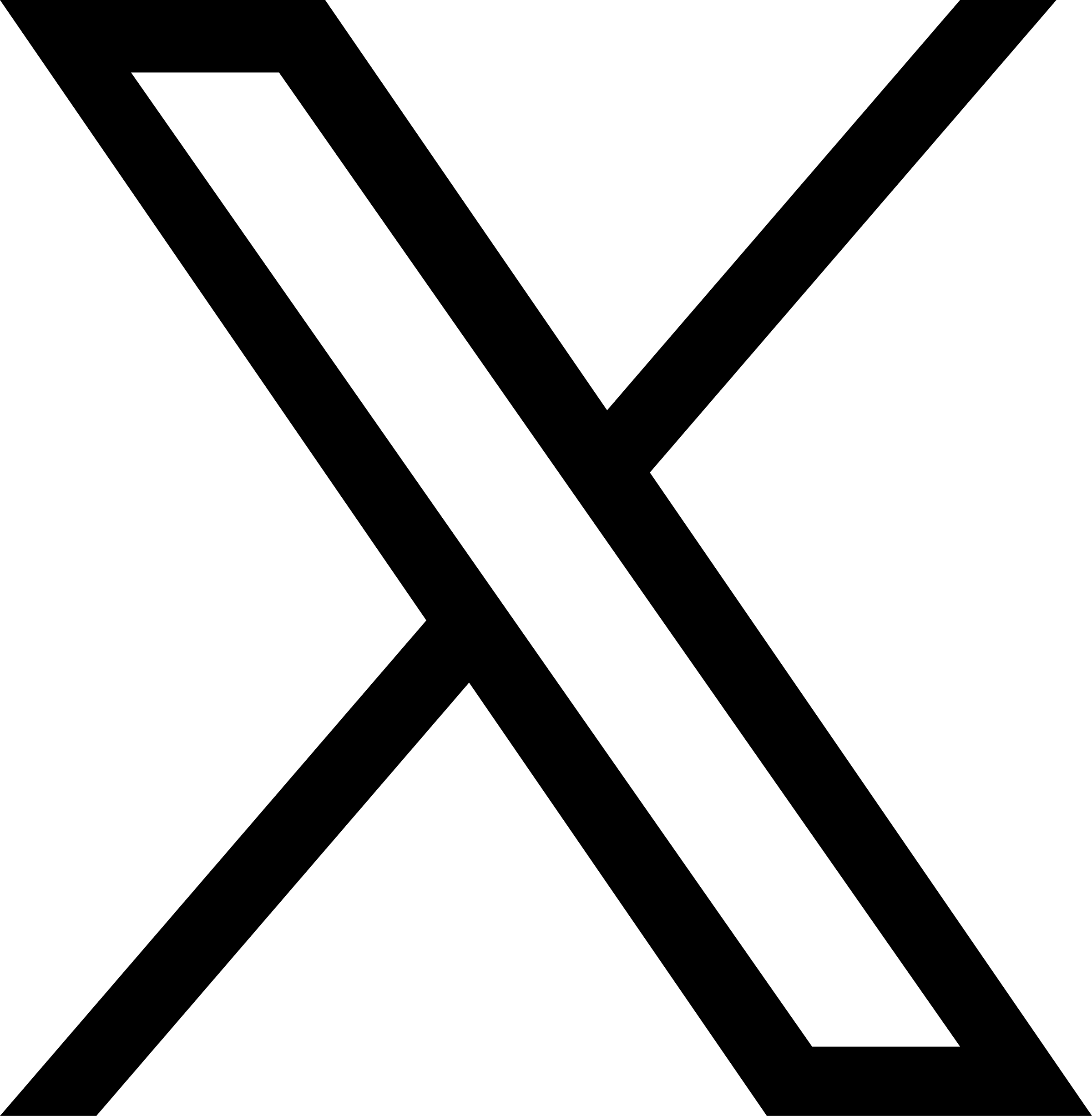漁師になろうとは思わなかった
玄関を開けると、目の前に穏やかな須賀漁港が広がる。光洋水産代表の櫻井さんは、先祖代々漁師を営む家系で、常に海がそばにある環境で育ってきた。しかし、子どものころに漁師になりたいと思ったことは一度もなかったという。
「祖父は当時から海藻の養殖をしていましたが、たまに手伝いをすることはあっても、船酔いするので船に乗ることはなかったですね。漁師は真冬でも朝4時前には海へ出ます。こんなに寒くて暗いのに海に行くなんて、考えられないと思っていました(笑)」

高校卒業後は税理士を目指していたという櫻井さん。けれど、どうしてもサラリーマンになるイメージが沸かず、一方で、祖父の手伝いをするうちに少しづつ漁師の仕事に興味が湧いていったという。
あるとき、ワカメの種苗(しゅびょう)作りをする知り合いの漁師が、高齢で後継者もいないため、事業をたたむという話を聞いた。種苗作りは技術が必要で、生産者のなかでもそれができる事業者は数えるほど。漁師のほとんどは、種苗を購入してワカメを養殖しているのだそうだ。
「ワカメの種苗作りができる人って本当に少ないんです。それが途絶えてしまったら、ワカメの養殖漁が衰退してしまいます。できる人がいないからこそ自分がその技術を受け継ぎたいし、チャンスだとも思いました」
そこで櫻井さんは「種苗作りを教えてくれませんか」と門を叩き、技術を継承した。どうせ事業をたたむならと教えてもらえることになったが、普通なら誰にも教えることのない技術なのだそうだ。「僕はラッキーだったんです」とにこやかに話す。
失敗続きの種苗作り
23歳でワカメの種苗作りをはじめた櫻井さんだが、一筋縄ではいかなかったようだ。
「最初の年はすべて失敗しました。そりゃそうですよね、簡単にできるならみんなやっていますから。種がなければ養殖業は商売になりません。お客さんには何度も怒られましたけど、それでも種を待っている人がいるから続けてこれました」
ワカメは、春先になると根元部分のメカブから小さな遊走子(ワカメの元)が多量に放出される。これを顕微鏡で確認しながら、採苗器に付着させていくのだそうだ。その後、水槽で成長させるのだが、「ここからが難しいんです」と櫻井さんは言う。
「種苗作りを教えてくれた師匠は、太陽光を使ってカーテンで光を調節しながら育てていました。けれど、うちは外から光が入りにくい構造だったこともあり、効率的に光を取り込んで育てるために蛍光灯を使うことにしました。でも、明るさの調整が難しくて、光を当てすぎても、当たらなくてもダメで、調整がうまくできるようになるまで5年かかりました」

地道な試行錯誤を繰り返し、ようやく軌道に乗ってきた2016年に会社を設立した。漁師の高齢化が課題となるなかで、若き櫻井さんの力は町全体に活気を与えている。
ワカメの可能性を広げていく
櫻井さんに、船を出してもらい松島湾の養殖場まで案内してもらった。


穏やかな松島湾の海一面に張られた縄には、等間隔で種糸が挟み込まれている。10月末の取材時にはまだ小さな芽のような状態で、ここから私たちのおなじみのワカメに成長していくのだそうだ。縄は1本50〜60mあり、約70cmの間隔で種糸を埋め込んでいく。何百本もある縄に手作業で種付けをし、毎日のように成長を確認し、収穫する。果てしなく地道な作業のすえに、私たちの食卓へ届けられているのだ。

ワカメにも個性がある。外洋で育つワカメは、荒波にもまれ肉厚に育つ。一方で穏やかな内海で育つワカメは肉うすでやわらかい。「一般的に肉厚なワカメの方が好まれますが、茎までやわらかいワカメも格別です。このおいしさをもっと多くの人たちに知ってもらいたいんです」と櫻井さん。
ワカメは日本の食卓には欠かせない食品のひとつだ。みそ汁や酢の物にしていただくのが一般的だが、櫻井さんは新しい食べ方をどんどん提案していきたいという。今回の商品はその一歩目となるだろう。噛めば噛むほどに旨味が広がる希少な「剣山わかめ」を、ぜひ味わってほしい。
文・奥村サヤ 写真・株式会社ル・プロジェ